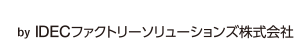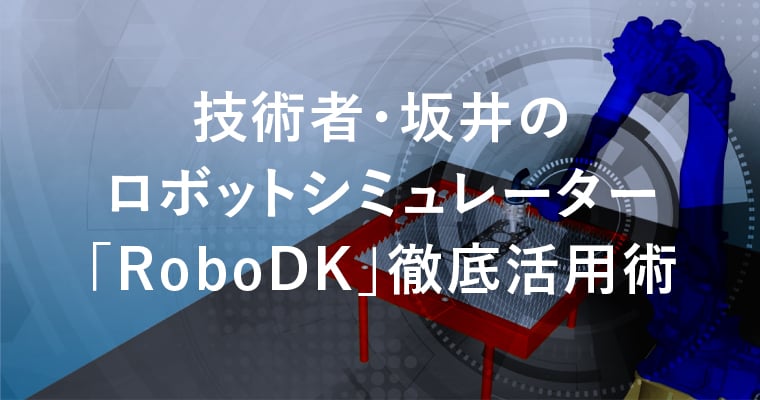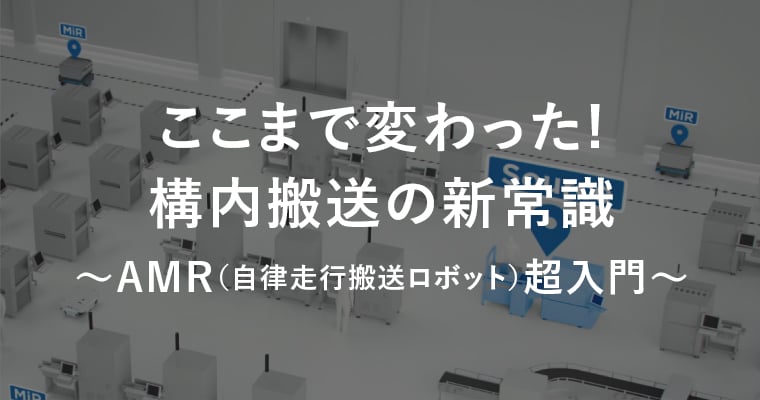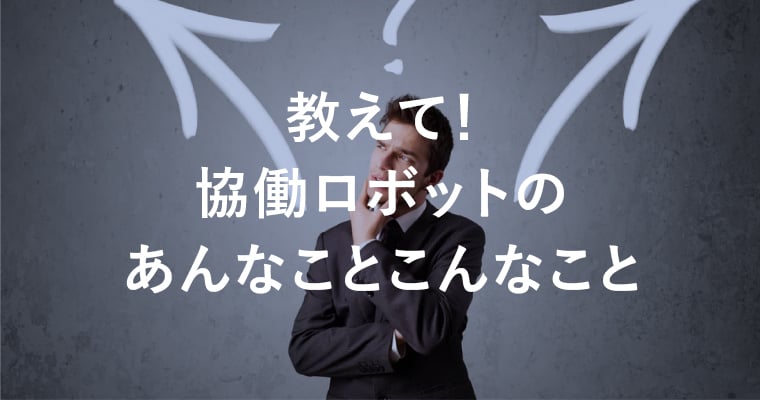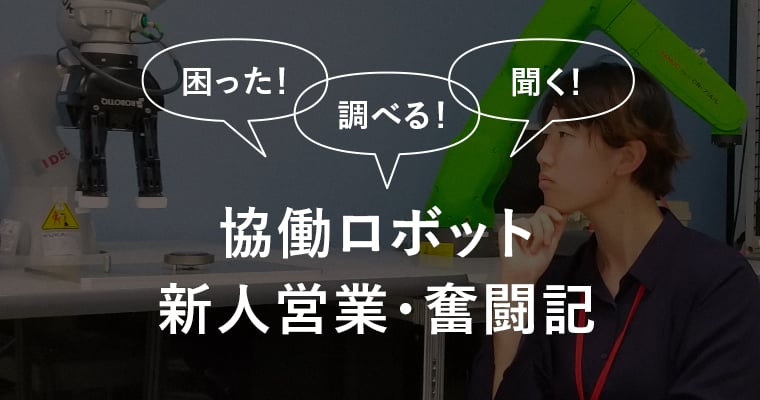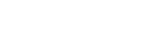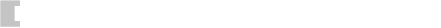セーフティリードアセッサの岡田です。
協働ロボットの登場から十数年。試行錯誤の時期を経て、いよいよ本格的な普及期が訪れていることを感じています。
そのような状況の中、2024年にご相談を頂き、私たちが実施した安全コンサルティングの事例から、協働ロボット導入を進める製造現場の安全に関する共通の課題が見えてきました。どのようにすれば、課題をクリアし、安全性と生産性が両立した協働ロボット導入を円滑に進められるのか、解説していきます。
協働ロボットの登場と製造現場における安全の考え方の遷移
協働ロボットは、2012年米国のリシンク・ロボティクス社が発売した「バクスター(双椀型)」から始まったといわれています。協働ロボットとは、人との協働作業空間で使用するための安全機能が搭載された安全柵無しで、人と作業スペースを共有しながら作業できるロボットです。
協働ロボットが登場するまで、産業用ロボットは人との衝突のリスクが大きいため柵で囲われ、人と隔離された状態でないと利用できませんでした。特に日本では、労働安全衛生規則で産業用ロボットの運転時にはロボットとの衝突によって人がけがをする可能性があれば安全柵等を使用しなければなりません。そのような中、2013年に厚生労働省からこの安全柵等を使用しなくてもよい条件が通達という形で示されて協働ロボット導入検討が開始されました。
このように、協働ロボットの歴史自体は新しく、2025年現在でまだ登場から十数年というところです。
その後、2016年ぐらいから製造現場への協働ロボットの導入ブームが訪れています。製造現場にこぞって協働ロボットが導入された時期でした。導入の理由としては「安全柵がいらなくなるので生産ラインのどこかに導入しよう」「周りが導入しているので当社も導入してみよう」など・・・特に明確な理由があるわけでもなく、何ができるかお試しでの導入という考えが多くを占めていました。
そんな意識での導入ですので、導入はしてみたものの、人との衝突が受け入れられず、結局、産業ロボットと同じように安全柵を設置したとか、人が作業するほうが効率良かったなど、協働ロボットに最適なアプリケーションを見出すことができずに導入を諦め、ブームの熱が冷めた後は、活用できなかった企業では協働ロボットが倉庫の片隅に眠っている、そんな状況を招きました。また、協働ロボットでありながら、実際に人との協働作業でロボットが使用されているケースも今ほど多くはありませんでした。
その一方、この間、確実に進行していたのが労働生産人口の減少による人手不足です。
労働生産人口とは、生産活動の中心的な年齢層である15歳から64歳の人口を指し、労働の中核的な担い手として経済と社会保障を支えていると考えられている層です。
統計でみますと、1995年をピークにその後は緩やかに減少を続けています。そして、その現象は今後も止まることはないと予測されています。
その労働生産人口の減少が製造現場に本格的に影響が与え始めたのが、コロナ禍が開けての2023年頃からではないでしょうか。
私の見立てでは、コロナ禍で人と人が距離を取って働く必要が生じ、そのために協働ロボットの再評価が始まりました。本気で人とロボットが同じ作業環境で協働できる設備を実現する、本来的な意味での協働ロボットの活用の時代が訪れたように思います。
人とロボットが近接して働くため、当然ながら人にとの接触は避けることができません。働く人が怪我をすることは、企業にとっては絶対に避けて通らなければならないことです。企業の信用にも関わりますので、今までの人と機械を隔離する安全方策から人と機械の協働作業空間における安全方策に考え方を切り替え、それを実践するようになってきています。
以上、協働ロボットの登場から今日までの製造現場の「安全」について振り返りました。
ではこのような状況下で、製造業が現在、製造現場の安全に関してどのような課題を感じているのか、2024年のご相談事例をもとにご紹介していきます。

2024年の安全コンサルティング事例の紹介
日本国内に本社を持ち、グローバルに展開しているA社
<ご相談時の課題>
海外で協働ロボットやAMRの導入が進んでいるため、グローバル展開を見据えた際には、協働ロボットを人との協働作業環境下で運用する必要がある。協働作業環境下では、安全柵等による物理的な隔離をしないので、協働ロボットやAMRとの衝突は避けられない。
ただし、安全は機械設備側で対処しなければならないというような、機械安全に厳格な現状のままの社内基準では、協働ロボットが人と衝突すること自体が受け入れられず導入の妨げの要因のひとつとなっている。
<コンサルティング内容>
まずは状況をヒアリング、社内に協働ロボットの人への接触を受容する土壌を作りたいという要望に応えるため衝突試験を実施。社内への共通コンセンサスを作る事をベースに、協働ロボットの導入推進を支援。
主に国内向けに製品を製造しているB社
<ご相談時の課題>
既に直面している採用難と将来的な人手不足を理由に、協働ロボットの導入の検討を始めたが、製造現場側が柵無しの状態でロボットと人が同じ空間で働くことに難色を示している。
生産技術部門としては、第一歩としてテスト導入を行い社内の理解を得ようと考えてはみたものの、具体的にどのように進めれば受け入れてもらえるか、明確な答えを持てずなかなかスタートできない。
<コンサルティング内容>
柵無しで利用できることが協働ロボットの最大の利点であり、ロボットとの衝突が軽傷以下のリスクしかないと判断された設備であっても衝突を一切受け入れないという考え方では、柵無しで協働ロボットを使用することは不可能ということを説明。
その上で、実際に衝突試験を製造現場の方々に公開実施して、数値や実機で安全性を実感してもらえるようにまずは衝突試験実施をサポート。
依頼内容から見えてきた、協働ロボットの安全に関する課題の共通点
いずれの企業のケースも、人手不足解消や生産性向上のため、協働ロボットを導入しなければならないという意識は高いものの、その一方で導入を急ぐあまり安全性が軽視されないかを危惧されご相談を頂く背景があります。ご依頼者は協働ロボット導入が思うように進まないジレンマを抱え、なんとかしたいという現状打開の思いで相談されるケースが多いように見受けられました。
詳しくお話を伺うと、協働ロボットが登場する以前の「安全基準(主に産業用ロボットに関する労働安全性規則)」に縛られ、協働ロボットが人と衝突してもけがをしないように制御できると知識ではわかっていても、そもそもロボットと人の衝突はだめ!という感覚にとらわれていることが原因のひとつとなっていることが浮かび上がってきました。
産業用ロボットに関する労働安全性規則の条項ではロボット運転中は人がけがをしないように「人が近づけないように安全柵で隔離する」もしくは「近づいてしまった場合は止める」という意味合いの項目があり、これを守り長い間産業用ロボットを導入してきたため、協働ロボットであっても今までの経験上、人と接触する前に「止める」事が感覚として大前提となってしまっているようです。
さらにお話を進めると、そのようなケースでは、生産効率を高めたい生産技術部署と人の安全を最優先とする安全系部署の利益相反の問題が存在しているように感じられました。それぞれの役割を追求するあまり、部分最適になっていることに意外と気づかれていない、そんなケースも散見されます。
私たちが提供する安全コンサルティングの価値とは
そもそも「絶対安全」は存在せず、リスクアセスメントを実施し、適切な安全方策を施すことで「許容できるリスクの状態=安全」を確保する事ができます。
これが製造現場における安全の基本的な考え方であり、この点に関して、いかにして社内の共通コンセンサスを作ることができるか、それができれば、協働ロボットの導入もこれまでよりスムーズに進むはずです。ただそのためには客観性が重要になるため社内の視点だけでは難しいところがあり、そこで私たち安全コンサルティングの出番となるわけです。

社内に存在する安全基準を協働ロボット導入後の環境や取り巻く社会の変化から見直すことにより、人とロボットが協働する環境での安全が確保され、生産性と安全性が両立した製造現場を作る事が可能になります。
いずれにしましても、ここで重要になるのが全体最適の視点での見直しであり、部門を超えた残留リスクへの経営的判断が求められます。
最後に-------将来予測「2025年以降、協働ロボットの安全に求められること」
労働生産人口の減少は残念ながら止めることはできないでしょう。直近では人手不足解消のため新たな採用活動を続けることになりますが、そもそも人での対応には限界があり、長期的には人手不足の問題を根本的に考え直すタイミングに来ているように思います。
では、どのように考え直したら良いのでしょうか。その有効な手段のひとつが、人との協働を前提とした協働ロボットの導入です。これまでもその取り組みには注力されてきたはずですが、お試しの域を脱することができず試行錯誤の時代であったことは否めません。
ただ協働ロボットの技術進化もあり、すでにお試しの期間は終わり、これまで難しいとされてきたアプリケーションにも本格的に導入が進んでいくフェイズに入ったと感じています。
より人と近い距離で協働ロボットを使用するケースも増えていきそうで、その場合の安全対策が「止める」という選択肢しかないとしたら生産性を阻害することになります。求められるのは、止める必要のない最適な設備づくりの視点ではないでしょうか。
生産性と安全性の両立。永遠のテーマとも言えますが、次のステージに向けて、あらためて生産プロセスや設備構成を0から考え直すタイミングが、今なのかもしれません。
お困りごとがありましたら、ぜひお気軽に当社の安全コンサルティングにご相談ください。
執筆者:
IDECファクトリーソリューションズ株式会社 セーフティ推進室 室長 岡田 和也
>>プロフィールはこちら